認知症は誰にでも起こり得る疾患ですが、生活習慣によって発症リスクは変化します。
特に近年では、食習慣が脳の健康に影響を与えることが明らかになりつつある状況です。脂質や糖質、塩分の多い食事は、生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、脳機能にも影響し、認知症リスクを高める要因になり得ると考えられています。
日々の食事内容を見直すことは、将来的な認知症予防につながる大切な一歩です。
この記事では、認知症になりやすいとされる食べ物や、予防に効果的とされる食品、バランスの良い食生活を送るためのポイントについて解説します。
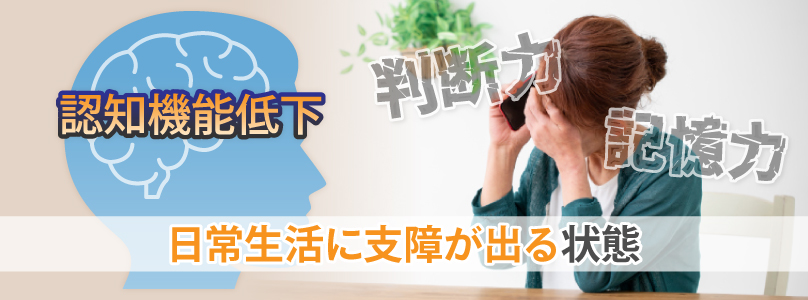
認知症とは、脳の病気や障害などによって、記憶力や判断力といった認知機能が低下し、日常生活に支障が出る状態を指します。高齢になるほど発症リスクは高まり、誰でもなる可能性のある疾患です。
認知症にはいくつかのタイプがあります。最も多いのがアルツハイマー型認知症で、脳神経が徐々に変性し、脳の萎縮が進むことによって発症します。もの忘れから始まり、進行はゆるやかです。
次いで多いのが、脳梗塞や脳出血などによって起こる血管性認知症です。このタイプでは、障害された部位によって症状に偏りが出やすく、「まだら認知症」と呼ばれることもあります。
高齢化が進む日本では、認知症は個人の問題にとどまらず、社会全体で向き合うべき課題とされています。
記憶力が急に悪くなった原因|考えられる疾患や対処法についても解説

認知症発生のメカニズムはまだ分かっておらず、予防方法や治療法も不明です。
しかし、食習慣は脳の健康と関係しているとされており、日々の食事内容が中長期的に認知機能へ影響を及ぼす可能性も指摘されています。特に、脂質や糖分、塩分を多く含む食品を継続的に摂取することは、生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、脳の働きにも影響を及ぼす要因と考えられています。
運動習慣や睡眠習慣の改善に加えて、食事にも注意すれば、ある程度認知症発生のリスクを減らす効果が期待できるでしょう。
飽和脂肪酸は、動物性の脂肪や一部の加工食品に多く含まれる、脂質を構成する脂肪酸の一種です。飽和脂肪酸の過剰摂取は、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)値を上昇させる要因とされており、動脈硬化や脳血管障害のリスクを高める可能性があると指摘されています。これらの循環器系疾患は、血管性認知症のリスク因子とも重なるため、食生活の見直しが重要とされます。
代表的な食品としては、牛肉や豚肉の脂身を多く含む部位、鶏皮、チーズ、ラードなどが挙げられます。例えば、豚のかた肉(脂身付き)100gには39.2gの飽和脂肪酸が含まれており、牛のリブロース脂身も100gあたり26.44gと高い数値です。
出典:食品成分データベース「肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/かた/脂身つき/生」
出典:食品成分データベース「肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/リブロース/脂身/生」
バターや乳脂肪入りのホイップクリームにも、同様に高濃度の飽和脂肪酸が含まれています。バターやクリームを大量に使用する洋菓子にも飽和脂肪酸が多く含まれており、ケーキやクッキーなどを多く食べる方は摂取量が多くなりがちです。
日常的にこれらの食品を過剰に摂ることで、血中コレステロール値の上昇や肥満の要因になる可能性も指摘されています。
飽和脂肪酸の摂取を控える工夫としては、赤身肉を選ぶ、乳製品は低脂肪タイプを選択する、揚げ物を控えて蒸す・茹でるといった調理法を取り入れることが挙げられます。食材の選び方や調理方法を見直すことで、過剰摂取を防ぐことが可能です。
トランス脂肪酸は、加工食品や肉類に多く含まれる、油脂の加工や高温処理などにより生成される脂肪酸です。摂取量が多くなると、心疾患のリスクを高める可能性があるとされており、食品から積極的に摂取する必要はないと考えられています。
日本国内の研究では、10年間にわたり約1,600人を追跡した調査によって、血中トランス脂肪酸の濃度が高い群で認知症の発症リスクが約1.6倍に上昇したと報告されています。
出典:九州大学「「血中トランス脂肪酸の上昇が認知症発症に関与する可能性を報告:久山町研究 」(衛生・公衆衛生学分野 二宮利治教授)」
トランス脂肪酸は以下のような食品に含まれる成分です。
特に、マーガリンやショートニングは、水素添加という工程で製造される際にトランス脂肪酸が生成されやすくなります。また、牛や羊などの反すう動物の体内でも微量のトランス脂肪酸が生成されるため、牛肉や乳製品にも天然由来のものが少量含まれています。
現在では企業の取り組みにより含有量が抑えられつつあるものの、加工食品や外食の利用が多いと摂取量が増加しやすいため、成分表示の確認や日常的な食品選びが重要です。トランス脂肪酸の摂取量は1日あたり総摂取エネルギーの1%に相当する量にすることが、世界保健機関(WHO)などでも推奨されています。
糖尿病や肥満は、脳血管性認知症やアルツハイマー型認知症のリスク要因とされています。特に高血糖状態が続くと、脳内の神経細胞にも悪影響を及ぼす可能性があると考えられているので、血糖値の急上昇につながる糖分は控えたほうがよいでしょう。
糖分の多い食品として代表的なものには、以下のようなカテゴリーがあります。
糖質の摂取量を調整するためには、白米を玄米や五穀米に変える、小麦粉をふすま粉や大豆パウダーに変える、甘い菓子類の頻度を減らす、乳製品は無加糖の商品を選ぶといった工夫が効果的です。また、血糖値の急上昇を避けるために、食物繊維を食事に取り入れるとよいでしょう。
塩分(食塩)の過剰摂取は高血圧の一因とされており、脳血管障害を招きやすくなることで、結果的に血管性認知症のリスクを高める可能性があると報告されています。
また、藤田医科大の研究では、塩分の多い食事が神経細胞に影響を及ぼす仕組みが動物実験で確認されました。塩分摂取によって脳内の特定のタンパク質が変性し、認知機能に悪影響を及ぼす可能性が示唆されています。
出典:日本経済新聞「藤田医科大、食塩過剰摂取に起因する認知症の発症メカニズムを解明」
カップラーメン、カップそば・うどん、漬物類、塩鮭、梅干しなどは代表的な塩分の多い食品です。また、ソースやしょうゆなどの調味料にも、塩分が多く含まれています。
加えて、ウインナーやハムなどの加工肉にも塩分が含まれており、加工食品や惣菜を日常的に摂ることで、知らないうちに塩分摂取量が増加することもあります。
世界保健機関(WHO)は1日の塩分摂取量を5g未満とすることを推奨していますが、日本人の平均摂取量は9.8gのため、減塩意識を持ちましょう。

認知機能の維持に役立つとされる食品には、脳や血管の健康に関与する栄養素を多く含むものが挙げられます。特に、青魚や野菜、果物などに含まれる特定の成分は、記憶力や判断力を支える働きがあると報告されています。
例えば、青魚に多く含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)は、脳の構成成分の1つであり、神経細胞の働きに関与する成分です。DHAのほか、血流を良好に保つEPA(エイコサペンタエン酸)もサバやイワシ、サンマ、アジといった魚に豊富に含まれます。
また、緑黄色野菜や豆類、果物などには、葉酸やビタミンC、ビタミンEが豊富な食品も多いです。これらの栄養素は、体内の酸化ストレスを軽減し、動脈硬化のリスク低下にも寄与すると考えられています。
ほかにも、認知機能の維持に良いとされている食べ物は、以下の通りです。
ターメリックに含まれるクルクミンは、脳内のアミロイドβ蓄積を抑制する可能性が示唆されています。
コーヒーのクロロゲン酸は抗酸化作用があると考えられています。
緑茶に含まれるカテキンは、抗酸化作用が強いとされる成分です。
大豆製品に含まれるレシチンは、神経伝達物質の材料になります。また、納豆に含まれるナットウキナーゼは血流改善に寄与するとされています。
オリーブオイルに含まれるオレイン酸は、血中脂質の調整や動脈硬化の予防に効果があるとされています。
ポリフェノールによる抗酸化作用が注目されています。ただし、過度の飲酒は認知機能低下のリスクがあるので、適量を摂取しましょう。
認知症のリスクを減らしたい場合は、個々の食材だけに注目するのではなく、食事全体の組み立てや食習慣の見直しが重要です。ここでは、認知機能の維持に向けて意識したい食事法のポイントを4つ紹介します。
| バランスの良い食事をする |
|---|
| 栄養バランスの取れた食事は、脳の健康を支える基本とされています。たんぱく質、炭水化物、脂質に加えて、ビタミンやミネラルなどの補助的な栄養素も意識的に摂取しましょう。魚介類や野菜、果物、海藻、豆類など、幅広い食品を取り入れることがすすめられています。 |
| 摂取カロリーに気をつける |
|---|
| 過剰なカロリー摂取は肥満を招きやすく、肥満は高血圧や糖尿病といった生活習慣病の引き金になります。これらは認知症の発症リスクと関連があるとされているため、日常的にエネルギー量を管理し、体重の維持に努めることが大切です。 |
| 塩分が多い食事を控える |
|---|
| 塩分の摂りすぎは高血圧を引き起こし、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害に発展する恐れがあります。脳血管性認知症の要因となるため、1日あたりの食塩摂取量は厚生労働省の目標値である男性7.5g未満、女性6.5g未満を意識して抑えることが求められます。あわせて、塩分排出を促すカリウムを含む野菜や果物の摂取も有効です。 |
| 間食や糖分を控える |
|---|
| 糖分の多い食品を頻繁に摂取すると、血糖値が上がりやすくなり、糖尿病のリスクが高まります。糖尿病はアルツハイマー型認知症とも関係があるとされているため、クッキーやケーキ、清涼飲料などの摂取は適量にとどめ、野菜や食物繊維の多い食品を選ぶように心がけましょう。 |
脂質や糖分、塩分の多い食品は、生活習慣病や脳血管障害のリスクと重なり、認知機能の低下に影響を与える可能性があります。
一方で、青魚や野菜、大豆製品などは、抗酸化作用や血流改善に関与する栄養素を多く含んでおり、認知機能の維持に役立つとされています。こうした食品をバランスよく取り入れることで、長期的に脳の健康を支える効果が期待できるでしょう。
食事のポイントとしては、栄養バランスを意識すること、カロリーと塩分の摂取量を適切に管理すること、糖分を控えることなどが重要です。
日々の食習慣を整えることは、認知症の発症リスクを軽減するだけでなく、全身の健康維持にもつながります。将来を見据え、できることから取り組むことが大切です。
記憶力低下は20代からはじまるの!?
記憶力が低下しても平気?
なんで歳を取ると忘れっぽくなるの?
そんな疑問にこちらのページで答えています。
エネルギー補給に!
MCTは短時間で体のエネルギーになる為、50年以上前から手術後のエネルギー補給として使用されています。
集中したい時に!
集中力を維持しながら勉強したり作業したい時は、短時間でエネルギーになるMCTを効率的に補給するのがGood!
運動のサポートに!
MCTは運動との相性良し!筋肉が脂肪燃焼型に移行するため「めざしたいボディ像」を持ってる人にもおすすめ!
健康かわら版はキリッと元気でさえざえとした生活を目指す皆様が気軽に日常でお試しいただける予防法やチェックリストなどの様々な読み物を医師監修で取り上げています。
キリッとPQQをお買上げのお客様には最新号を商品と一緒に同梱してお届け。バックナンバーはこちらのリンクから無料でダウンロード頂けます。